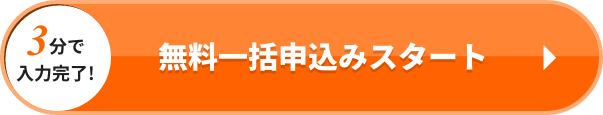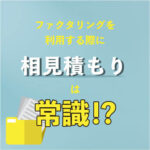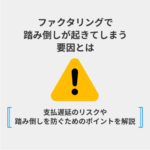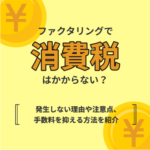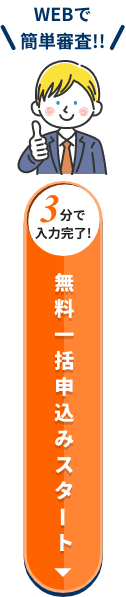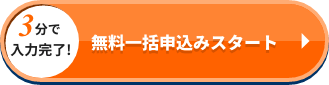売掛金の回収と遅延損害金(利息)の請求について解説
目次
CLOSE経理処理上のミスや取引先の資金繰り悪化など、何らかの事情で売掛金の支払いが所定の期日よりも遅れてしまうことがあります。「売掛金の回収が遅れた場合、遅延損害金を請求できるのか」が気になる方はいるのではないでしょうか。この記事では、売掛金の支払いが遅れると遅延損害金が発生するのかについて解説します。
遅延損害金が発生するケースとは?
遅延損害金とは、 金銭債務に関わってくるものです。金銭債務とは、支払手形や買掛金、借入金、債券など、将来に定めた期日までに他者へ所定の現金を引き渡すという契約上の義務です。
そのため、遅延損害金は債務者が約束の期日までに所定の金額を支払えなかった場合に、その損害を償うために支払われる金銭のことを指します。
遅延損害金が発生する可能性がある3つの契約
一般的に遅延損害金は以下の3つの契約に定められています。
- 売買契約
- 金銭消費貸借契約
- 賃貸借契約
売買契約とは、売り主が目的物の「財産権」を買い主に移転し、買い主がその代金を支払うという取り決めのことです。
意外に感じるかもしれませんが、私たちが日常生活で当たり前のように行っている買い物でも売買契約が成立しています。少額の買い物は現金で一括払いのケースが多く、売買契約だと言われてもなかなかピンとこないでしょうが、クレジットカードなどによる後払いやショッピングローンによる分割払いでは、その支払いが遅れると「遅延損害金」が発生します。
消費貸借契約は「受け取った物を消費する代わりに、それと同じ種類・品質・数量の物を返すこと」を意味し、返す物を金銭に特定しているのが金銭消費貸借契約です。
賃貸借契約は、不動産業界でよく用いられている言葉です。貸す側は目的物の使用(および目的物から発生した収益の取得)を許可する一方で、借りる側はその賃料を支払うことを約束した取り決めです。
売掛金の遅延損害金に関する3つの注意点
ここでは、売掛金の遅延損害金に関する3つの注意点を紹介します。
1.取り決めがない遅延損害金も請求できる
売掛先(モノやサービスを利用した側)は「金銭債務」を負っていることを意味しています。この「金銭債務」に対し、所定の期日までに相応の金額を支払わない場合には、「遅延損害金」が発生します。
つまり、決済日を過ぎても売掛金が送金されないケースにおいても、「遅延損害金」が発生し、本来なら売掛先はその分を加算した金額を支払わなければならないのです。
売掛金の支払いが期日に間に合わなかった場合の「遅延損害金」は、契約時に法律上の制限にかからない範囲内で自由に定められます。先に述べたように、契約時にで「遅延損害金」について取り決めていなかった場合も請求が可能で、そのケースでは法定利息を適用することになります。
2020年4月1日の民法改正以降、法定利率は年利3%となっています。なお、その利率は3年毎に見直される変動性となっているので、その都度確認しましょう。
なお、先程は売掛先の立場から「金銭債務」と表現しましたが、モノやサービスを提供した側から言えば、売掛金は「売掛債権」と呼ばれる債権の一種です。債権には支払いの期限が定められており、あらかじめ具体的な取り決めが行われていなかったとしても、期日が守られなければ、債権者には遅延損害金を請求する権利があります。
2.厳密には「遅延損害金」と「遅延利息」は異なる
「遅延損害金」は「遅延利息」と呼ばれることもありますが、厳密に言えば、利息とは異なるものだと位置づけられます。利息とは、金銭を貸し付けたことの対価として支払われる金銭のことを指しています。
つまり、金銭の貸し付けに対して発生するものであって、売買代金や請負代金、賃貸料などに対して利息は関わってきません。唯一、金銭消費貸借契約において発生した「遅延損害金」については「延滞利息」とみなすことができます。
3.遅延損害金のある売掛債権は回収できない可能性がある
発生から1年が経過した場合は、「遅延損害金」の分を元本に組み入れたうえで、その合計額に法定利率を乗じた「遅延損害金」を請求できます。
しかし、もっとも、1年以上も支払いが滞っているのは、売掛先の資金繰りが非常に厳しい情勢で、まさに「無い袖は振れない」というパターンなのかもしれません。法的には「遅延損害金」を請求可能であっても、貸し倒れ(売掛金回収不能)となるリスクが高まっていると考えたほうが無難かもしれません。
また、売掛債権には時効があり、期間は5年です。期間を過ぎると遅延損害金だけでなく、売掛金も請求できなくなってしまうため注意する必要があります。
こういった貸し倒れのリスクを避けるためには、債権管理(与信管理)を行うことが重要です。債権管理とは、売掛金を管理する業務のことです。取引先が代金を支払える状況を確認したり、債権管理表を作成したりすることで、入金漏れを防ぎます。
また、貸し倒れリスクを軽減する方法として、ファクタリングがあります。ファクタリングは、期日前の売掛債権を売却して資金を調達する方法です。手数料がかかるため、売掛債権より金額は下がってしまうものの、貸し倒れによる損失を抑えられます。
ファクタリングについて知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
即日入金可能なファクタリングサービス5選|メリットや注意点、選び方のポイントを紹介
まとめ
売掛先の支払いが遅れた場合、あらかじめ約束を交わしていなくても「売掛債権」の所有者が「遅延損害金」を請求することは法的に認められています。遅延損害金のある売掛債権の場合は払えない何らかの事情を抱えていて、貸し倒れとなる可能性が高いとも受け止められます。そのため、債権管理やファクタリングなど対策を講じることが大切です。