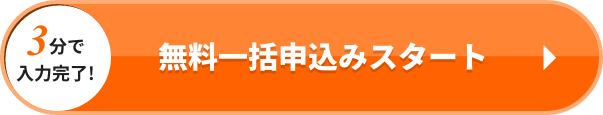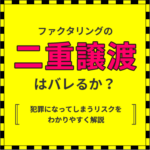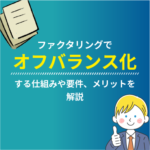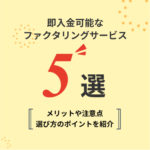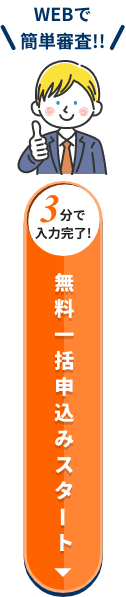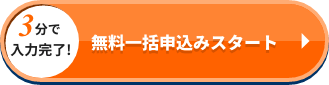売掛債権の時効はいつまで?未回収リスクや債権回収を行う方法を解説
目次
CLOSEビジネスの場で活用される売掛債権ですが、時効があることをご存知でしょうか?時効による債権消滅を防ぐためには、売掛債権の時効についての知識や債権回収を行うための方法を知っておくことが大切です。
この記事では、売掛債権の未回収リスクや売掛債権の時効、債権回収を行う方法を紹介します。
売掛債権の意味と未回収リスク
「売掛債権」とは、売掛先(取引先)に対して販売したモノやサービスの代金を受け取る権利のことです。逆に売掛先は、所定の期日までにその代金を支払う債務を負っています。
ところが、現実には期日を迎えても売掛先が代金を支払ってくれないケースも発生します。単なる経理手続き上のミスではなく、経営難などを理由に支払いが滞ったり、遅延したりすることが起こりうるのです。
とはいえ、未回収のまま放置し続けていると、「消滅時効」が適用されてしまいます。消滅時効とは、一定期間にわたって行使されなかった権利を消滅させる制度です。
法律で定めた期間内に権利を行使しなかった場合は、代金を請求する権利を失ってしまい、本来受け取るはずだった収入がなくなってしまいます。そのため、自社で保有する売掛債権の時効については十分に注意する必要があるのです。
2020年4月1日施行の民法改正で売掛債権の時効期間は5年に
2020年4月1日施行の民法改正により、2020年4月1日以降に発生した売掛債権の時効までの期間は5年になりました。
2020年3月31日以前の民法では、債権の「消滅時効」が原則10年と定められていたものの、細かく種別したうえでそれぞれに通常よりも期間の短い「短期消滅時効」が別途定められ、実務上は短期のもののほうが適用されていました。
こうしたことから、具体的にいずれの「短期消滅時効」が該当するのかの判断が難しかったり、そもそも短縮される合理的な理由が見当たらないという不平不満が生じたりしていたことから、2020年4月1日から施行された改正民法では「短期消滅時効」が廃止され、債権に関しては次の2つのうち、どちらか早いほうに達した場合に「消滅時効」を迎えることになりました。
- 債権者が権利を行使できることを債務者が知った時点から5年
- 債権者が権利を行使するようになった時点から10年
ただし、債権者が権利を行使するようになった時点で、債務者もその内容を知っていると捉えられるため、一般的には5年の時効期間が適用されるケースが多いです。
旧民法下では1〜3年で時効を迎えるケースが主流だっただけに、「売掛債権」を保有している側にとっては画期的な法改正だと言えるでしょう。ただし、2020年3月31日以前に発生した債権については、改正前の民法が適用されることになります。
また、長期化されたとはいえ、不払いの状態が続くといずれは権利を失ってしまうのも確かです。時間が経てば経つほど、支払ってもらえる可能性も低くなってしまいます。
期日に遅れている売掛債権を回収する8つの方法
売掛先の事情がどうであれ、モノやサービスを提供した以上、その代金を受け取るのは正当な権利です。適切な措置を取って「債権回収」を進めることになります。債権回収とは、未回収の「債権」を債務者に支払わせるために行う活動を意味しています。具体的な「債権回収」の手段としては、以下のようなものがあります。
- 電話や面談などを通じた交渉
- 内容証明郵便の送付
- 民事調停
- 支払督促
- 少額訴訟
- 仮差押
- 通常訴訟
- 強制執行
電話や面談などを通じた交渉電話や面談などを通じた交渉
電話や面談などを通じた交渉はその言葉の通りで、発注担当者や経理担当者、あるいは経営者などに支払いを求めるというものです。支払いに応じられない事情次第では、分割払いなどの譲歩条件を提示しながら回収の実現を図ります。
内容証明郵便の送付
売掛先が交渉に応じようとしなかったり、条件を譲歩しても支払いが滞ったりした場合は、もっと強硬な手段を講じることになります。
その最初に打つべき手は内容証明郵便で、その際に作成した謄本を通じて、誰がいつ、誰に対してどのような内容の文書を郵送したのかを郵便局に証明してもらえます。ただ、あくまで内容証明郵便は、「このままでは然るべき措置を講じます」といった姿勢を示す渓谷のような意味合いで、支払いに関する強制力は有していません。
民事調停
内容証明郵便を送付しても支払いに応じなければ、いよいよ法的な手続きが必要になると考えられます。民事調停は裁判官や調停委員によって構成される調停委員会が債権者と債務者それぞれの言い分を踏まえたうえで、問題の解決を図るという制度です。
支払督促
民事調停に持ち込んでも回収に至らない場合には、いよいよ訴訟などの法的な手続きが必要となってくるでしょう。その一つが支払督促です。
支払督促とは、裁判所を介して債務者に未回収となっている債権の支払い督促を「通知」するという手続きです。簡易裁判所が債務者に支払いを督促し、相手が異議を申し立てない場合は「仮執行宣言」を経た後に強制執行が可能となるほか、支払督促を申し立てることで時効の完成を猶予できます。
ただし、債務者側が異議を申し立てた場合はその効力が失効してしまいます。当然、債権者側は納得できるはずがなく、訴訟沙汰へと進んでいくのが一般的でしょう。
少額訴訟
少額訴訟は60万円以下の売掛債権の支払いを求める場合にのみ利用できるもので、即日に判決が出ます。しかし、その内容に対して債務者側が異議を申し立てた場合は審理をやり直すことになります。
通常訴訟
「通常訴訟」は少額訴訟よりも手間暇がかかり、何度も証拠提出などの手続きが求められるものの、相対的に解決を期待できる可能性が高いと言えます。これは、裁判所が双方の主張や証拠などを精査し、原告の主張する権利の存在を審理する制度です。こうした訴訟の提起は、時効の完成を猶予することにもつながります。
仮差押
財政悪化で「売掛債権」の不払いに陥っている場合は、売掛先が法的措置の判決前に保有財産の処分を進める恐れもあります。そういった行為を防ぐための手続きが仮差押です。
「仮差押」とは、債務者の銀行預金や不動産などの処分を公に禁じる措置です。
強制執行
債権者側が勝訴したり、和解が成立したりした場合であっても、未払いが続けば「強制執行」と呼ばれる措置に踏み切ることになるでしょう。強制執行は裁判所が強制的に債務者に請求権を実効するというものです。
債務者が法人の場合、たとえ口座残高がほとんどゼロで実質的に差し押さえられなかったとしても、以降の銀行取引は停止され、債務者は事業の運営が現実的に困難となってきます。また、他の取引先にも不審がられる懸念があることから、比較的早期の支払いを促すことを期待できます。
売掛債権には時効がある!放置せず、債権回収を進めよう!
2020年4月1日以降に発生した売掛債権の時効は5年です。そのまま放置していると、当然ながら計上した売上よりも実収入は減少し、状況次第では財政状況を圧迫しかねません。売掛債権の支払いが遅れている場合は「債権回収」を検討する必要があります。自社が保有する売掛債権はしっかり管理し、安定した資金繰りを行いましょう。