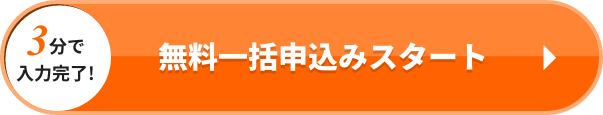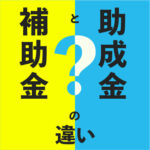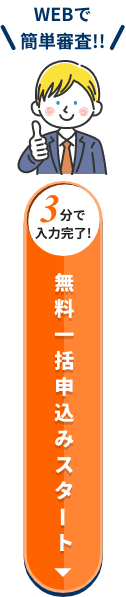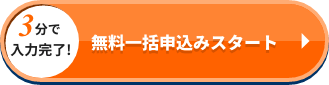補助金と助成金の違いを比較!利用する際の注意点も紹介
目次
CLOSE補助金と助成金は、ともに事業者への支援を目的とした制度ですが、その目的や対象、申請方法などに違いがあります。事業者がこれらの制度を有効に活用するためには、補助金と助成金の違いを正しく理解することが重要です。
記事では、補助金と助成金の主な違いについて、複数の観点から比較していきます。また、補助金・助成金を活用する際の注意点も解説しているので、事業者の方はぜひ参考にしてください。
補助金とは?
補助金とは、国や地方自治体から、法人や個人事業主などの事業者に支給される、返済不要のお金です。主に経済産業省や中小企業庁が所管しています。
代表的な補助一覧
以下は、代表的な補助金の一覧です。国や地方自治体の目的に応じてさまざまな補助金が提供されています。
いくつかの補助金について詳しく紹介していきます。
例えば、小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が経営計画を作成し、その計画に沿って行う販路開拓等の取り組みを支援するための補助金です。補助上限額は50万円で、補助率は2/3となっています。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする制度です。補助率は1/2以内で、補助上限額は50万円から450万円まで、事業の類型によって異なります。
助成金とは?
助成金も、国や地方自治体が事業者に対して支給する、返済不要のお金です。主に厚生労働省が所管しています。
代表的な助成金一覧
以下は、代表的な助成金の一覧です。主に雇用に関連したものが提供されています。
いくつかの助成金について詳しく紹介していきます。
例えば、キャリアアップ助成金は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するための制度です。正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成されます。
業務改善助成金は、中小企業事業主が、労働者の労働条件の改善や生産性の向上に資する設備・機器の導入や人材育成を行う際に、その費用の一部を助成する制度です。
【項目別】補助金と助成金の違い
補助金と助成金の違いを以下にまとめました。
| 項目 | 補助金 | 助成金 |
|---|---|---|
| 目的 | 新規事業の立ち上げ、地域経済の活性化、社会貢献活動の推進 | 雇用の安定化、スキルアップ支援、労働条件の改善 |
| 主な管轄 | 経済産業省 | 厚生労働省 |
| 支給額 | 数百万円〜数十億円 | 数十万円〜数百万円 |
| 支給要件 | 審査があり、採択されないと受給できない | 要件を満たせば、原則受給できる |
| 公募期間 | 数週間〜1ヶ月 | 通年で公募されている |
| 主な財源 | 税金 | 雇用保険料 |
それぞれの項目を詳しく見ていきましょう。
目的
補助金と助成金は、ともに事業者への支援を目的としていますが、その目的には違いがあります。補助金は主に新規事業の支援、地域振興、公益につながる事業の促進などを目的としており、事業者の新たな取り組みを後押しすることに重点を置いています。
一方、助成金は雇用の促進、能力開発、労働環境の整備など、労働に関する課題への取り組みを支援することが主な目的です。
管轄
補助金は、主に経済産業省や中小企業庁が管轄しており、経済の活性化や中小企業の支援を目的とした施策の一環として実施されています。
一方、助成金は主に厚生労働省が管轄しており、労働者の福祉の向上や雇用の安定を図ることを目的としています。
支給額
補助金の支給額は、事業の規模や内容によって大きく異なりますが、数百万円から数億円規模のものまであります。
一方、助成金の支給額は、補助金と比べると小さい傾向にあり、数十万円から数百万円程度が一般的です。
支給要件
助成金は、一定の要件を満たせば原則として受給できるのが特徴です。助成金の要件に合致していれば、申請すれば受給できる可能性が高いといえます。
一方、補助金は競争率が高く、審査を経て採択される必要があります。補助金の採択率は制度によって異なりますが、申請しても受給できない可能性がある点に留意しておきましょう。補助金の申請にあたっては、事業の優位性や実現可能性を明確に示すことが重要になります。
公募期間
助成金の多くは通年で公募されているため、事業者は年間を通してタイミングを選んで申請することができます。
一方、補助金は期間限定での公募が一般的です。公募期間は数週間から1ヶ月程度と比較的短い傾向にあります。補助金の申請を検討している事業者は、公募期間を見逃さないよう注意が必要です。
財源
補助金と助成金では、財源にも違いがあります。補助金の主な財源は税金です。国や地方自治体が予算を組み、その中から補助金を支出しています。
一方、助成金の主な財源は雇用保険料です。事業主が支払う雇用保険料が原資となっており、一部は税金も使われています。ただし、財源が異なるだけで、どちらも事業者の活動を支援するという点は変わりません。
補助金・助成金を利用する際の注意点
ここでは、補助金・助成金を利用する際の注意点を紹介します。
補助金は後払いであり、支給されるまでに時間がかかる
補助金は事業の実施後に支給される後払いであるため、事前に自己資金や融資、ファクタリングなどで必要な資金を用意しなければなりません。
また、補助金の支給までには審査や手続きに一定の時間がかかります。事業終了後、実績報告書の提出や審査を経て、支給が決定するまでに数ヶ月を要することもあります。
補助金の交付決定を受けても、すぐには資金が入ってきません。そのため、事業の計画段階で、補助金の支給時期を見越した資金計画を立てることが重要です。
経費対象となる期間が決まっている
多くの補助金・助成金には、事業実施期間が定められており、その期間内に発生した経費のみが補助・助成の対象となります。事業期間外に発生した経費は、たとえ事業に関連していても、補助金・助成金の対象外となってしまうため注意が必要です。
例えば、事業開始前の準備段階で発生した経費や事業終了後の経費は、原則として補助・助成の対象になりません。そのため、事業の計画段階で、対象期間を正確に把握する必要があります。その期間内に必要な経費が発生するようにスケジュールを組むようにしましょう。
申請書類は事前に準備する必要がある
多くの補助金・助成金では、申請書類の提出が必要です。内容は制度ごとに異なり、事業計画書や収支予算書、見積書など、様々な書類が求められます。審査の担当者に納得するためにも、事業の概要や必要性、経費の内訳などを詳細に盛り込むことが重要です。
申請書類の不備や誤りは審査に大きな影響を与えかねません。そのため、申請書類は事前に十分な時間をかけて準備し、内容を確認することが大切です。
法令違反になると給付停止の対象となる
補助金・助成金の不正受給や目的外使用、虚偽の申請などは、法令違反にあたる可能性があるため、絶対にしないでください。法令違反が発覚した場合、補助金・助成金の給付が停止されるだけでなく、返還請求を受けることもあります。
さらに、悪質な場合は刑事罰の対象となることもあるため、十分な注意が必要です。例えば、補助金・助成金で購入した設備を私的に使用したり、申請書類に虚偽の記載をしたりすることは、不正受給にあたります。
補助金・助成金を活用する際は法令を遵守し、適切な使用を心がけましょう。
補助金・助成金の違いを理解して利用を検討しよう!
補助金と助成金は、事業者支援を目的とした制度ですが、主な目標、所管官庁、給付金額などに違いがあります。補助金・助成金を活用する際は、自社の事業内容や規模、ニーズに合わせて、適切な制度を選択することが重要です。
また、申請にあたっては、要件の確認や提出書類の準備、期限の厳守など、注意点を押さえておく必要があります。補助金・助成金を上手に活用して、事業の発展や改善につなげていきましょう。
こちらの記事も一緒に読まれています。
ファクタリング活用時にお役立てください♪