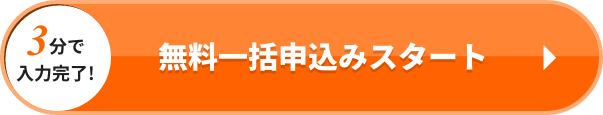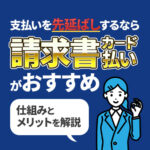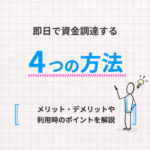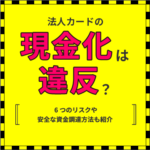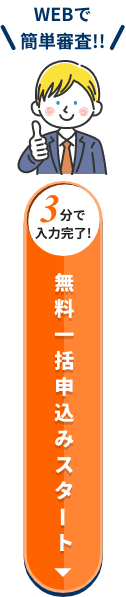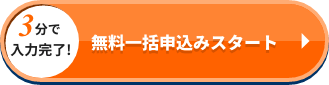支払いサイトとは?一般的な期間や決め方、延長・短縮する方法を解説
目次
CLOSE取引を行うとき、日本の商取引は掛け取引が一般的ですが、「支払いサイト」という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
資金繰りの改善や取引条件の交渉において、この支払いサイトの理解は非常に重要です。この記事では、支払いサイトの概要や一般的な長さ、延長・短縮する方法などを紹介します。ぜひ参考にしてください。
支払いサイトとは?
支払いサイトとは、商品・サービスを仕入れた締め日から、代金を支払う期日までの期間です。企業間の取引では、商品やサービスの仕入れ後、すぐに支払いを行うのではなく、一定期間の猶予を設けます。
身近な例でいえば、クレジットカードの利用額が確定してから、実際に口座から引き落とされるまでの期間と同じです。企業にとって支払いサイトは、キャッシュフローや資金繰りに影響する重要な要素の一つです。
支払いサイトからわかる企業の財務状態や経営効率
企業の財務状態を把握するための重要な3つの要素として、売上債権・棚卸資産・仕入債務があります。この中でも支払いサイトと密接に関係するのが「仕入債務」です。
仕入債務とは、商品やサービスを仕入れた後、まだ支払いが完了していない金額のことです。
一般的に買掛金として計上され、貸借対照表では負債に分類されます。この仕入債務の金額や回転率を見ることで、企業がどのように資金を運用しているか、支払いの効率性はどうかなど、経営状態を読み取ることができます。
<仕入債務回転率>
仕入債務回転率は、仕入債務がどれくらいの頻度で支払われているかを示す指標です。計算式は以下のとおりです。
| 仕入債務回転率 = (売上原価 ÷ 仕入債務)× 100 |
この数値が高いほど支払いが効率的に行われていることを示しています。目安としては、1,200%以上が望ましいとされています。
<仕入債務回転期間>
仕入債務回転期間は、仕入れから支払いまでの平均的な期間を表す指標です。計算式は、以下のとおりです。
| 月単位の場合:仕入債務回転期間= 1ヶ月ごとの仕入債務 ÷(売上原価 ÷ 12) 日単位の場合:仕入債務回転期間 = 1日ごとの仕入債務 ÷(売上原価 ÷ 365) |
この期間が長いほど手元に現金が残るため、支払いまでの余裕があることがわかります。一方で、売り手側にとって期間が長いのは、未回収リスクが高くなることに留意しておきましょう。
一般的には、40日以下が目安とされていますが、業界や取引内容によって適正な期間は異なります。
支払いサイトと回収サイトの違い
支払いサイトと回収サイトは、同じ取引を異なる立場から見た表現です。支払いサイトは買い手側から見た支払までの期間、回収サイトは売り手側から見た代金回収までの期間を指します。
例えば、30日サイトの取引であれば、買い手にとっては「支払いまでに30日の猶予がある」という解釈になり、売り手にとっては「代金回収まで30日かかる」という捉え方になります。
支払いサイトの一般的な期間
企業間取引における支払いサイトは、主に30日・60日・90〜120日の3つのパターンがあります。業界や取引規模によって異なりますが、それぞれの特徴を見ていきましょう。
月末締め・翌月払い(支払いサイト30日)
最も一般的な支払いサイトが、「月末締め・翌月末払い」、いわゆる30日サイトです。例えば、1月に商品やサービスを仕入れたなら、2月末に支払うことになります。
月単位で売上や仕入れを管理できるため、双方の経理処理がしやすいことから、中小企業から大企業まで幅広く採用されています。
買い手側には1ヶ月の支払い猶予があり、売り手側も比較的早く代金を回収できるため、バランスの取れた支払いサイトといえるでしょう。
月末締め・翌々月払い(支払いサイト60日)
60日サイトは「月末締め・翌々月末払い」と呼ばれ、1月の取引であれば3月末に支払いが行われます。
30日サイトと比べて買い手側の資金繰りに余裕が生まれる一方、売り手側は代金回収までに最大3ヶ月かかることもあります。
手形取引(支払いサイト90〜120日)
手形取引の場合、支払いサイトは90〜120日と長期になることがあります。これは手形が請求書の締め日ではなく、手形の振出日から支払期日までの期間が加算されるためです。
ただし、2024年11月からは約束手形の支払いサイトは60以内に短縮されることが決定しています。60日を超える手形取引は行政指導の対象となる見通しです。
これは中小企業の資金繰り改善を目的とした施策で、今後は支払いサイトの短縮化が進むと予想されます。手形取引を主体としている企業は、支払い方法の見直しを検討する必要があるでしょう。
支払いサイトの決め方・考え方
支払いサイトは取引先との関係性や業界の慣習、自社の資金繰りなどを考慮して決めていく必要があります。ここでは、売り手側、買い手側それぞれの視点で、支払いサイトの決め方・考え方の違いを見ていきましょう。
【売り手側視点】回収サイトは短く設定したい
売り手側にとって、支払いサイトは短いほうが資金繰りの面で有利です。早期に代金を回収できれば、その資金を次の仕入れや事業投資に回せるためです。
特にスタートアップ企業や成長期の企業は、支払いサイトが長すぎると運転資金が不足する恐れがあります。極端な場合、売上は好調なのに資金が足りずに倒産する、黒字倒産のリスクも考えられます。
企業の資金繰りを滞りなく行うためにも、売り手側は可能な限り支払いサイトを短くしようとするのが基本です。
【買い手側視点】支払いサイトは長く設定したい
一方、買い手側は支払いサイトが長いほうが都合が良いといえます。支払いまでの期間が長ければ、その分手元資金を他の用途に活用できるためです。
ただし、売り手側にとっては回収サイトが長くなることになるため、承諾を得にくいのが実情です。
また、下請代金支払遅延等防止法では、下請業者の支払いサイトは60日以内とするのが原則です。そういった観点からも、支払いサイトは30日〜45日、場合によっては大企業との取引で60日程度とするのが一般的です。
支払期日が土日・祝日である場合の対応
支払期日が土日・祝日になってしまうこともあるでしょう。支払期日が土日・祝日である場合、業界慣習や契約内容によって前営業日や翌営業日になるのが普通です。
トラブルを防止するため、取引開始時に支払期日の扱いについて明確に取り決めておきましょう。
売り手として回収サイトを短縮するには?
支払いサイトが長く資金繰りに不安がある場合、いくつかの対応策があります。以下で具体的な方法を見ていきましょう。
取引先に交渉する
可能であれば、取引先と交渉してみましょう。ただし、「資金繰りが厳しい」という理由だけでは相手の理解を得にくいため、交渉には工夫が必要です。
例えば、支払いサイトを短縮する代わりに取引金額を割引く、発注ロットを大きくするなど、双方にメリットのある提案を心がけます。
手形割引を利用する
手形での支払いを受けている場合は、手形割引の活用を検討しましょう。手形割引とは、満期日前に金融機関で手形を現金化するサービスです。
通常の支払いサイトより早く資金を得られる一方、手数料がかかるというデメリットもあります。ただし、融資と比べて審査が通りやすく、短期間で資金調達できるのが特徴です。手形の信用度が高いほど有利な条件で利用できます。
ファクタリングを利用する
ファクタリングは、売掛金を買い取ってもらうことで、早期に資金を調達できるサービスです。
2種類の方式があり、取引先に知られずに利用できる「2社間ファクタリング」と、取引先の承諾が必要な「3社間ファクタリング」があります。
3社間の方が手数料は安くなりやすいものの、取引先との調整が必要になります。企業の状況に応じて使い分けましょう。
「Payなび」では、一度の申し込みで複数のファクタリング会社に審査を依頼できます。オンラインで完結するため、最短60分での資金調達も可能です。手数料や入金スピードなど項目を比較して、自社にあったファクタリングを選べます。
買い手として支払いサイトを延長するには?
資金繰りの改善や運転資金の確保のため、支払いサイトを延長したいケースもあるでしょう。ここでは、買い手として支払いサイトを延長する方法を紹介します。
取引先に交渉する
支払いサイトの延長を希望する場合、まずは取引先との交渉を検討します。ただし、一方的な要望では相手の理解を得られにくいため、Win-Winの関係を意識した提案が重要です。
例えば、発注量を増やす、長期契約を結ぶ、支払い方法の見直しによる事務コスト削減を提案するなど、取引先にもメリットのある条件を示すことで、交渉が成立しやすくなります。
ただし、下請事業者との取引では60日を超える支払いサイトは法律違反となるため注意が必要です。
法人カードでの支払いを提案する
法人カードでの支払いを提案する方法もあります。法人カードでの決済であれば、支払いをまとめて翌月以降に計画的に行うことができ、支払いサイトを延長できます。
とはいえ、売り手の回収サイトに影響を受けることを懸念して、カード決済を断られるケースもあります。
請求書カード払いを利用する
最近では「請求書カード払い」というサービスも登場しています。これは、通常の振込支払いをカード決済に切り替えられるサービスです。具体的な流れとしては、利用者が代行会社に対してクレジットカードで決済し、代行会社が支払います。
振込も最短即日で入金されるため、取引先の資金繰りに影響を与えることなく、自社の支払いサイトだけを延長できます。
支払いサイトを延長するなら「カード払いくん」の活用がおすすめ
支払いサイトの延長を取引先と交渉するのは簡単ではありません。昨今は支払い期間の短縮化が求められる傾向にあり、交渉が難しくなっています。
そんな時に活用したいのが、請求書カード決済サービス「カード払いくん」です。カード払いくんでは、取引先との支払いサイトはそのままに、実質的な支払い期間を最大60日延長することができます。
例えば、月末締め翌月末払い(30日サイト)の取引で2月末が支払期日の場合、カード払いくんを利用すれば実質的な支払いを4月末まで延ばすことが可能です。
使い方は簡単で、支払いたい請求書をアップロードし、お手持ちのカードで決済するだけ。取引先には通常の振込として表示されるため、サービスの利用が知られることもありません。
支払いサイトに関してよくある質問
ここでは、支払いサイトに関してよくある質問をQ&A形式で回答していきます。
Q1:一般的な支払いサイトの長さはどのくらいですか?
最も一般的なのは「月末締め翌月末払い」の30日サイト、次に多いのが「月末締め翌々月末払い」の60日サイトです。30日サイトであれば、商品・サービスの取引が発生した月末に締めを行い、翌月末に支払いが行われます。
Q2:締め日と支払期日の違いは?
締め日は取引を締めて請求金額を確定させる日、支払期日は実際に支払いを行う日です。たとえば「月末締め翌月末払い」の場合を例に説明しましょう。
1月中に発生した取引は1月31日に締め(締め日)、その支払いを2月末に行う(支払期日)という流れになります。この場合、締め日から支払期日までの期間が支払いサイトです。
なお、締め日は必ずしも月末とは限らず、毎月20日締めなど、取引先との契約によって異なることもあります。
取引を行う際は、支払いサイトを意識しましょう
支払いサイトは、企業の資金繰りを左右する重要な要素です。売り手は回収サイトを短く、買い手は支払いサイトを長くしたいというのが基本的な構図ですが、取引先との関係性や業界の慣習を考慮しながら、適切な期間を設定しましょう。
また、取引先との交渉が難しい場合は、「カード払いくん」のような請求書のカード決済サービスを活用することで、実質的な支払期間を調整することも可能です。自社に合った方法を選択し、健全な資金繰りを目指しましょう。
こちらの記事も一緒に読まれています。
ファクタリング活用時にお役立てください♪